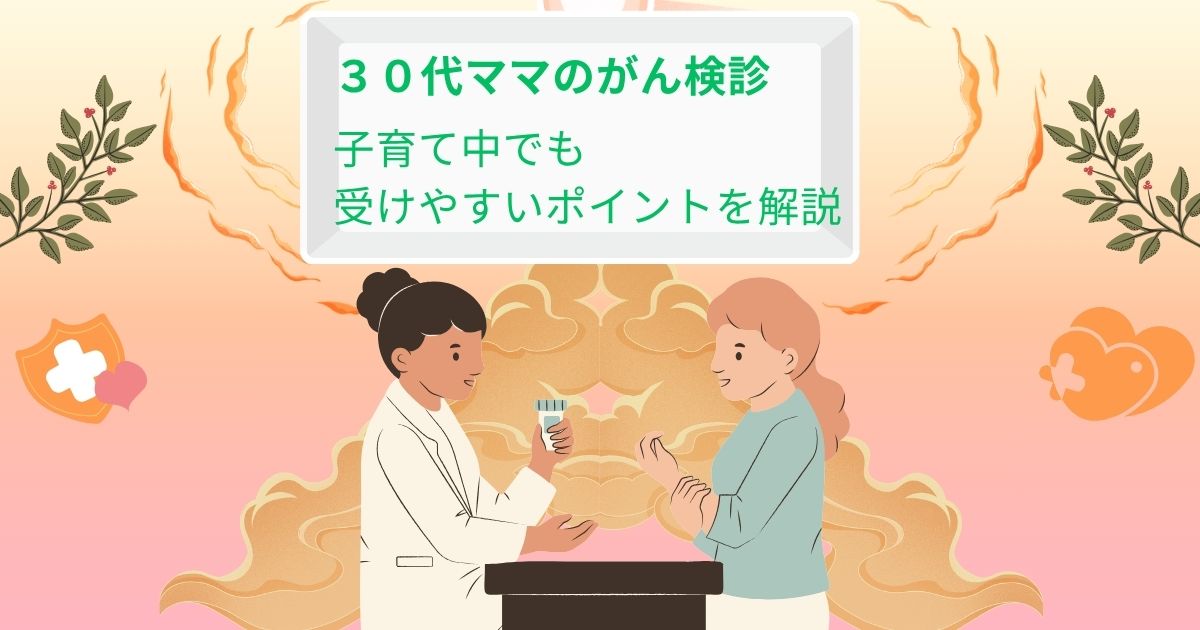「子育て中で忙しくて、自分のことは後回し…」そんな毎日を過ごしていませんか?
実は30代も、がん検診の対象となる年齢なんです。
「まだ30代だし、自分にはまだ早いんじゃないかな?」と思っていたら、もしかすると検診のタイミングかもしれません。
この記事を読むことで、30代ママが受けられるがん検診の内容や、所要時間、検査に必要な持ち物など、「これはどうなんだろう?」という疑問を解消できます。将来の安心のために、まずは「知る」ことから始めてみませんか?
30代からの「がん検診」、今のうちに知っておきたいこと

30代で対象になるがん検診は「子宮頸がん検診」
子宮頸がんは、がんになる前の段階ではほとんど自覚症状がありません。
おりものの変化や出血、痛みといったサインも出ないため、自分では気づきにくい病気です。
そのため、「まだ症状がないし、また今度行こう…」と検診を先延ばしにしてしまうと、早期発見のチャンスを逃してしまうリスクがあります。
実際、国立がん研究センターの2020年の統計では、子宮頸がんの罹患数は30代から増加し始めることが示されています。
仕事や子育てに追われている今こそ、自分のからだと向き合う時間をつくることが大切です。
子宮頸がんは、早期に発見できれば5年生存率は90%以上とされています。
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス|子宮頸部 統計情報(生存率)」
がん検診を受けることで、将来の自分自身、そして家族を守ることにもつながります。子育てに忙しい今だからこそ、自分のからだを知る最初の一歩を踏みだしてみませんか?
「乳がんは40代から」は本当?30代の今からできること
「乳がん検診は40歳から」と聞くと、「私はまだ関係ないかも」と思う方もいるかもしれません。
けれど、検診の開始年齢や、今からできることを知っておくだけでも、将来の安心につながります。
実は、乳がんは日本人女性に最も多いがんです。国立がん研究センターの2020年の統計でも、女性のがん罹患数において乳がんは1位と報告されています。
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス|乳房 統計情報(罹患)」
そんな乳がんへの備えとして、30代からできる大切な習慣が「ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)」です。
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス|乳がん 予防・検診(ブレスト・アウェアネス)」
これは自己検診のように「触って調べる」のではなく、ふだんの自分の乳房の状態を知り、少しの変化に気づけるようにすること。
「なんとなくいつもと違う…」と感じたら、早めに医師に相談することが大切です。
忙しい毎日でも、こうした小さな意識が、未来の自分を守る力になります。
がん検診は「私にはまだ早い」は思い込みかも?
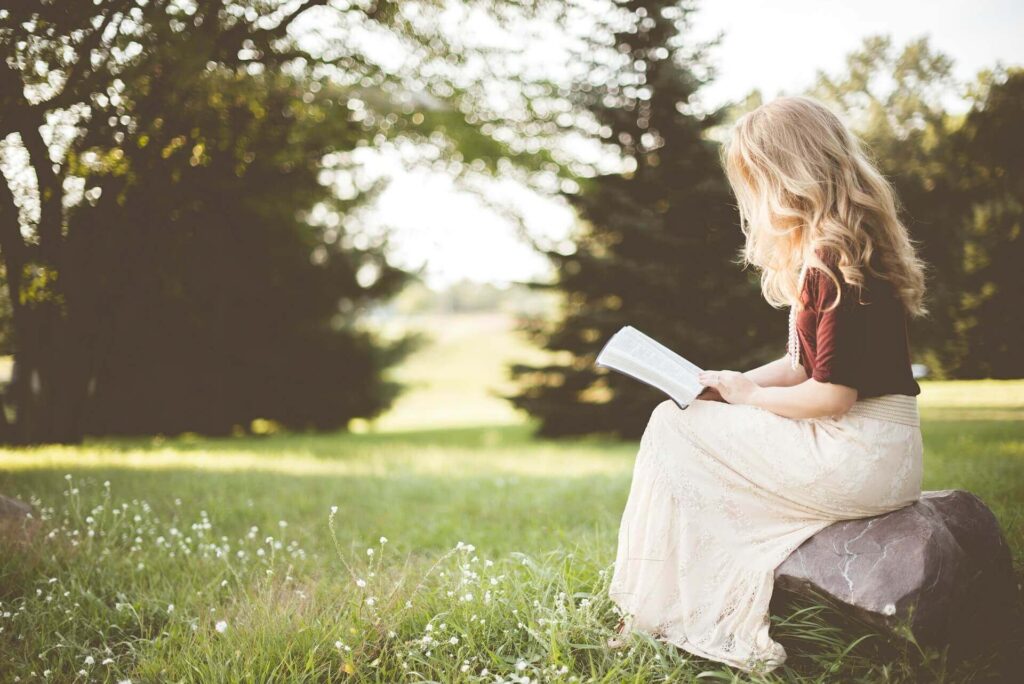
妊婦健診で検査済みでも安心しないで。2年後が次の目安
妊婦健診では、妊娠初期に子宮頸がんの検査を受けることが一般的です。妊娠中に受けた子宮頸がん検診から2年以上たっている場合は、そろそろ次の検診を意識するタイミングです。
子宮頸がん検診は、国が推奨する受診間隔として「2年に1回」が基本とされています。子育てや家事に追われる中で、つい自分のことは後回しになりがちです。
思い出した今こそチャンス。「いつか行こう」が積み重なる前に、今こそ自分の体と向き合う時間を持ってみてください。
がん検診は何歳から?知っておきたい年齢別の目安
子宮頸がんや乳がん以外にも、年齢によって推奨されているがん検診があります。
今すぐの対象ではなくても、「何歳でどんな検診が始まるのか」を知っておくと、これからの備えとして役立ちます。
下記は、国が推奨するがん検診の対象年齢と受診間隔の一覧です。
| 検診の種類 | 対象年齢 | 受診間隔 |
|---|---|---|
| 子宮頸がん検診 | 20歳以上 | 2年に1回 |
| 乳がん検診 | 40歳以上 | 2年に1回 |
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 毎年(1年に1回) |
| 肺がん検診 | 40歳以上 | 毎年(1年に1回) |
| 胃がん検診 | 50歳以上 | 2年に1回 |
※出典:国立がん研究センター「がん情報サービス|がん検診の一覧」
https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/about_scr01.html
忙しい人でも受けやすい!土曜検診や託児つきがん検診も
小さな子どもがいると、平日に自分のための予定を入れるのはなかなか難しいもの。がん検診も「行かなきゃ」と思いつつ、つい後回しになっていませんか?
しかし、土曜日に検診を受けられる医療機関や、託児サービスつきの検診日を設けている自治体も増えてきました。
たとえば、愛知県名古屋市では年3回土日にレディースがん検診があり、大阪府高槻市では保育つきのがん検診が実施されています。
出典
名古屋市【「レディースがん検診」の実施について】
高槻市【集団がん検診・予約制】レディースクリニック|保育付き検診
こうした取り組みは、全国の自治体にも徐々に広がりつつあります。
「仕事や育児でムリかも…」と思っていた検診も、少し調べてみるだけで、意外と身近な場所で受けられるかもしれません。
近くの自治体でも受けられる可能性があるので、ぜひチェックしてみてください。
子宮頸がんと子宮体がんの違い|検診でわかるのはどっち?
「子宮がん」と聞くと、ひとつの病気のように思いがちですが、実は2種類あるのをご存じですか?
それが「子宮頸がん」と「子宮体がん」です。
子宮頸がんは、子宮の入り口(頸部)にできるがんで、多くはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因とされています。
20代後半から30代にかけてかかる人が増えてくるのが特徴です。
一方の子宮体がんは、子宮の奥(体部)にできるがん。こちらは40代後半〜50代以降に多くみられます。
月経異常や閉経後の不正出血といった症状がきっかけで発見されるケースがあります。
出典
国立がん研究センター「子宮頸がん (子宮頸がんの原因と症状)」
国立がん研究センター「がん情報サービス|子宮頸部 統計情報(生存率)」
国立がん研究センター「がん情報サービス|子宮体がん(子宮内膜がん) 」
国立がん研究センター「がん情報サービス|子宮体部 統計情報(罹患)」
注意したいのは、「子宮がん検診」という名前に含まれる検査の中身です。
多くの自治体で実施されているのは、子宮頸がんの検診だけで、届く案内の多くも子宮頸がん検診のみです。子宮体がんの検診は含まれていないケースがほとんどです。
また、子宮体がんは現在、国が定める「がん検診」の対象外となっています。子宮体がんの検査は、人間ドックなどで、任意で受ける形式が一般的で、気になる症状があれば早めに婦人科を受診することが大切です。
実際にどんな検診が受けられる?堺市の例で解説
「じゃあ、具体的に何の検診を受けたらいいの?」そんな疑問に答えるために、今回は大阪府堺市の制度をもとに、30代の方が受けられるがん検診の内容や手順を紹介します。
多くの自治体でも同様の仕組みが採用されているので、お住まいの地域でも参考になるはずです。
対象年齢・費用は?堺市の子宮頸がん検診のしくみ

堺市では、20歳以上の偶数年齢の女性市民を対象に、子宮頸がん検診を実施しています。
2025年度(令和7年度)は、自己負担金が無料とされており、対象の方にとっては受けやすい年になっています。
また、堺市のホームページにある医療機関検索機能を使えば、
など、希望にあった医療機関を探せます。
出展:堺市けんしん総合サイト|受けよう!けんしん|がん検診|医療機関検索
受診に必要なもの・流れは?初めてでも安心のガイド
初めての子宮頸がん検診でも、持ち物と流れを知っておけば安心です。
■ 持ち物
保険証または運転免許証などの本人確認書類
受診券(あれば)
費用(自治体により一部負担が必要な場合もあります)
■ 検査内容と時間
問診
視診・内診
細胞診(子宮の入り口付近を綿棒でこすって採取)
検査自体の所要時間は約15分程度で、待ち時間を含めても通常は1時間以内に終了することが一般的です。
■ 服装のポイント
服装に特別な指定はありませんが、上下が分かれた服がおすすめ。
スカートや脱ぎ着しやすいズボンだとスムーズに受けられます。
まとめ
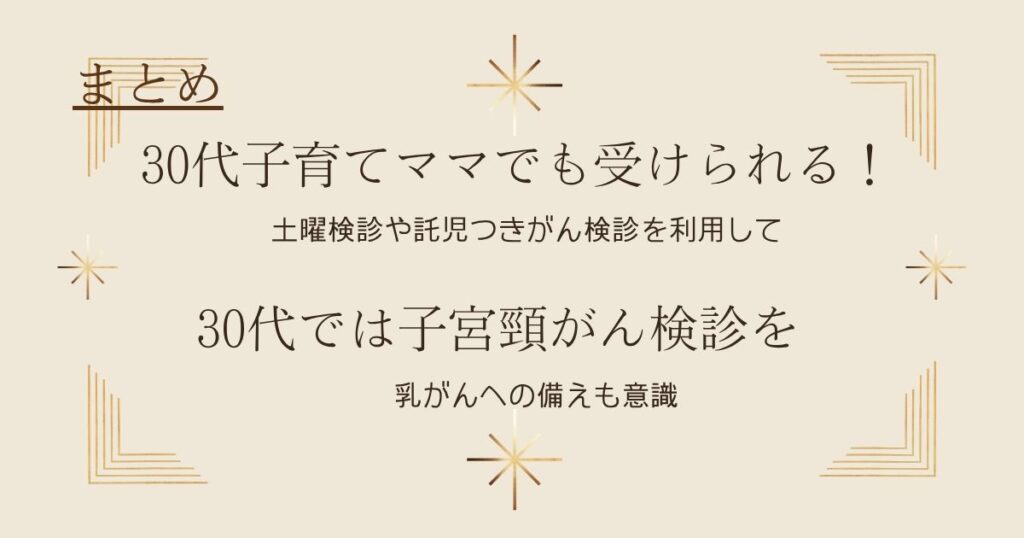
「忙しいからまた今度」と、がん検診はつい後回しにしてしまいがちです。
けれど、すこしの行動が、これからの自分自身と家族の安心につながります。
子育てや家事に追われる毎日の中でも、自分の体と向き合う時間を持つことは、未来への大切な投資です。
特に30代の女性にとって、今受けておきたいがん検診は「子宮頸がん検診」です。
思い出した今こそが、行動を起こすベストタイミングかもしれません。
まずは、お住まいの地域で実施されているがん検診について調べてみてくださいね。